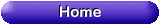|
秋 祭 り 石川県白山市(旧 石川郡鶴来町)月橋町町内会 平成14年9月吉日作成 平成17年更新 |
|
| 北国新聞(地元新聞)にて紹介 平成17年10月1日〜2日に開催 | |
 |
|
 |
|
 |
|
| 2005年10月1日撮影 | |
 |
渡り蜻蛉の半兵衛流棒振りの紹介 3年に一度 10月1日〜2日に開催 次回は令和2年に開催予定 西州誌によると槻橋村は鎌倉時代(1192年頃)に村造りされ神社も建立されていたものであり、文 明六年(1469年)室町幕府時代に槻橋(つきはし)豊後(ぶんごの)守(かみ)一族はこの村を領し、富 樫氏の代官槻橋弥四郎が住んでいたと言われ、神社名も槻橋神社となっています。 |
 |
槻橋の獅子舞(以下棒振り)は、明治二十八年(1895年)九月棒振りを習う為金沢の地黄(じおう)煎 町(ぜんまち)現在の泉野四丁目付近にあった半兵衛道場を訪ね、辻市太郎、池端六三郎ら九名 が入門を許可され以後明治三十六年八月まで二十三名が、八年間門弟として半兵衛道場て学び 発展させた力強い棒振りである。中でも五人棒は見応えがありますが、池端氏の手によるもので 旧鶴来や吉野谷村中宮方面までも指導したとされています。 半兵衛流で使用する衣装は、刺し子と袴で白足袋姿となっていて、袴は紺地に漢字の「渡」や蜻 蛉の図柄と水玉模様が染めぬかれたものであり、これは町田半兵衛が再興して家を継いだ渡辺 家で渡辺流と称し「渡」の文字を表したもので、門弟として認められた人のみが使用でき、当時は 斯界の憧れの袴であった。 |
 |
 はかま はかま |
 |
槻橋の獅子舞は、相棒・三人棒・五人棒は獅子をかまいながら互いか゛討ち合って先陣を争って 戦うが、最後には一緒になって獅子に戦いを桃み獅子を討ち"ヨイヤー"の掛け声で獅子は頭を だらりと下げ棒振りは終わる。 当日は先ず槻橋神社に奉納され、その後町内の家々を廻り「五穀豊穣」を感謝し"家の厄払い" 魔除け""悪魔払い"等を願って一軒一軒の前で棒振りをします。昭和十六年(1941年)頃までは本 物の太刀を使用し、暗くなると火花が飛びあいもの凄い迫力であったが、その後本物も無くなり現 在は木造の太刀のみされています。 |
 |
お囃子は三味線・笛・太鼓で形成されていましたが、戦時体制の頃から男子は戦場に赴く事とな り三味線を伝授できず、戦後旧鶴来より芸者さんを雇って行っていましたが、昭和四十四年の禁 止令により芸者がいなくなり伝承出来なくなった事が残念であり今後の課題であります。 蜻蛉(トンボ)は、水面上を飛び廻り水中・地上・空中で、年中生きるものとして子孫繁栄や強さを 示す印とされているものであり、勇壮な武術を取り入れた渡り蜻蛉の半兵衛流棒振りの伝統を守 り伝承する為三年に一度の催しとなっています。 |
 |
獅子頭は、長年使用されたので傷みがひどく、昭和二十九年に富山県井波町在住の彫刻師建部 豊氏の作による桐材黒漆塗りで大型の雄獅子が現在使用されています。 以前は刺し子・袴は個人持ちでありましたが、町民の深いご理解のもと平成十二年(2000年)に 刺し子・袴・諸道具類を新調することができました。 左記の画像は、平成14年に行われた時のものです。 |